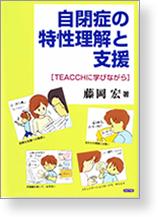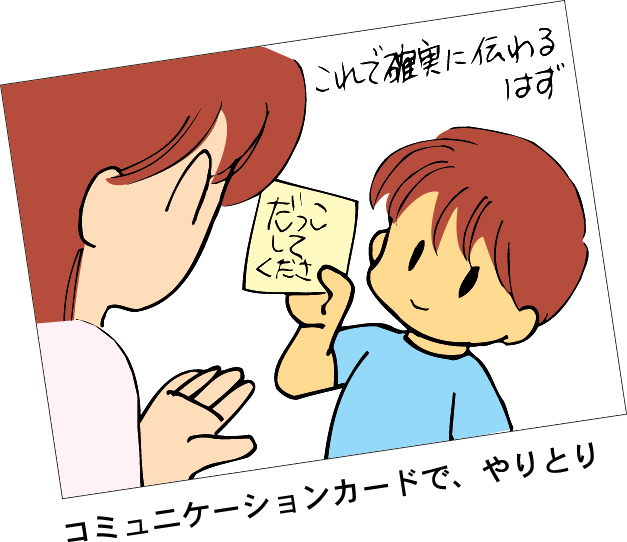第1部 自閉症の特性を理解する
1章 コミュニケーションに関する特性
1 相手の意図がうまく汲み取れない
2 相手に自分の意思をうまく伝えられない
2章 見え方・聞こえ方・感じ方に関する特性
1 自閉症の人の世界
(1)秩序のない、混沌とした世界
(2)〈どこから〉〈どこまで〉が、わかり
にくい
(3)いつまでも忘れられない
2 感覚が鋭すぎる(逆に、鈍すぎる)
(1)聴覚過敏
(2)触覚過敏
(3)味覚過敏
(4)その他の感覚特性
3 気づかれにくいさまざまな特性
(1)ここというところに注意を向けるのが
苦手
(2)完成までの手順を頭に描くのが苦手
(3)因果関係をとらえるのが苦手
(4)ことばの裏を読むのが苦手
4 〈特性理解〉の視点を持って支援を
3章 特性から見た〈視覚的手がかり〉の意味
1 耳からのことばを理解するのはむずかしい
2 目で見て理解するのは得意
3 自立的に行動できることの大切さ
4 手がかりのない中で生きることを強いる
5 思春期になって現われる問題
4章 自閉症と発達障害について
1 自閉症の3つの基本症状
(1)社会性の障害
(2)コミュニケーションの障害
(3)こだわり
2 自閉症と発達障害
(1)高機能自閉症
(2)アスペルガー症候群
(3)AD/HD
(4)「発達障害」という用語について
(5)「自閉傾向」ということばについて
3 診断は支援への橋渡し
*子どもの行動にどう対処するか
― 答えを導き出すための道筋
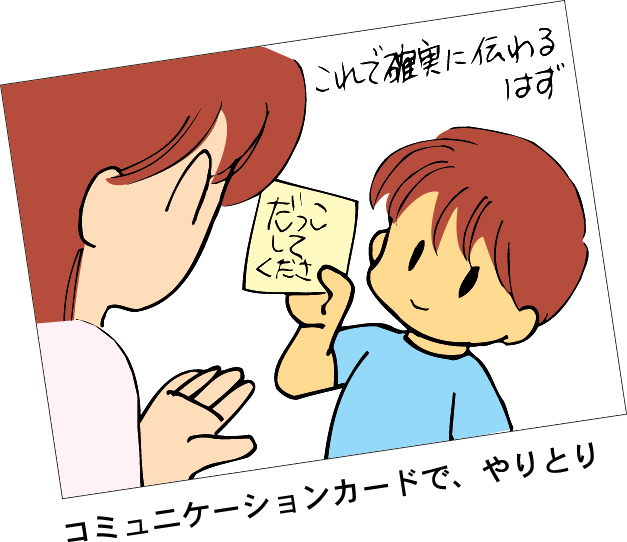
*イラストは「ぼくの絵日記」の方が描きました。
*はやと君のお母さんのホームページで、
「ぼくの絵日記」がご覧になれます。
http://www.geocities.jp/ekotan1689/ |
第2部 特性に沿って支援の方法を考える
5章 受信を助けるための工夫
1 場所で環境の意味を知る ―― 物理的構造化
2 時間の見通しを持つ ―― スケジュール
3 スケジュールのいろいろな工夫
4 活動の流れと終わりを知る ―― ワークシステム
5 見てすぐわかる ―― 視覚的構造化
6 見てすぐわかる、いろいろな工夫
7 〈構造化〉―― 二つの世界のかけ橋
6章 発信を助けるための工夫
1 コミュニケーションは楽しい、と思えるように
(1)コミュニケートしようとする“心”を育む
(2)コミュニケーションの機会をつくる
(3)楽に使いこなせる方法を身につけさせる
2 確実に伝えられる方法を教える
(1)カードを使うと、話しことばが伸びない
のでは?
(2)相手の注意を引く方法を教える
(3)「ノー」を正当に表現する方法を教える
3 コミュニケーションカードのいろいろ
7章 生活の中のコミュニケーション
1 ことばを話せる子どものための工夫
2 スケジュールを使って、卒園式の練習
3 手順書を使って、ボウリングを楽しむ
4 コミュニケーションの力をつけてくると
*〈よく見られる誤解〉について考える
第3部 医療・親さん・地域
8章 親さんとの出会い、TEACCHとの出会い
1 自閉症の人との出会い
2 「土曜学級」で出会った親さんたち
3 TEACCHから学んだこと
4 発達クリニックの現場から
9章 医療の役割と療育との連携
1 医療の役割
(1)診断の意味
(2)〈親の育て方のせいでなったのではない〉
ことの確認
(3)薬を飲む際のルール
(4)検査
(5)療育相談、カウンセリング、告知
(6)福祉制度や地域資源、参考図書の紹介
2 医療から療育へ
(1)調査の方法
(2)調査の結果
(3)調査結果についての考察
10章 自閉症の子を持つ親さんの世界
1 はやと君のお母さんの手記
2 私たちが親さんと協働する時
11章 学校と地域への願い
1 学校の先生方へのお願い
2 素晴らしい校長先生たちとの出会い
3 子どもと親さんにやさしい地域に
*この本でお話してきたことを、まとめてみます

|