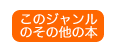谷口奈保子(たにぐち なおこ)
1942年9月5日 中国・奉天(旧満州)に生まれる
1965年3月 明治学院大学英文科卒業
1965年〜67年 日本オリベッテイ株式会社勤務
1981年3月 明治学院大学福祉学科卒業
1983年7月 「ぱれっと」を設立
以来22年間、東京・恵比寿で、知的障害者が地域であたりまえに
働き・暮らし・楽しむためのさまざまな拠点を創り出してきた。
1999年10月 スリランカに「Palette」を設立
2002年12月 「ヤマト福祉財団賞」を受賞
●目次●
1章 自立を教えてくれた母
五歳の時、満州から引き揚げてきた/北海道から奈良へ、そして東京へ/私の生き方の
転換期を支えてくれた母/演出を学んで、演劇をやるのが夢だった/セールスウーマン
を辞め、専業主婦に
2章 娘の死を無駄にしたくない
四歳の娘を小児癌で亡くす/闘病の日々、家族の危機/病児や親と苦しみを分かち合え
るのではないか/病院でボランティア活動を始める/「福祉」を学ぶために、もう一度
大学へ/筋ジストロフィーの青年の訴え/知的障害者との出会いの衝撃/「末期患児の
チームケア」を卒論のテーマに/チームケアを求めて、アメリカへ
3章 「地域と福祉」にめざめる
医療相談事業づくりの壁/地域活動の魅力/医療福祉から障害者福祉へ、難病児から知
的障害者へ/「青年教室」のボランティア活動の面白さ/疑問をぶつけ、答えを探した
かった/もう行政を待てない、とにかく始めなきゃ!
4章 街のまん中に、新しい出会いの場を! ――「たまり場ぱれっと」をつくる
障害者もボランティアも仲間として集える場/場所探しで思わぬ難題に/「ぱれっと」
の名前に託した願い/一般の地域住民が代表になる意味/ボランティアは楽しい時間を
共有する仲間として/ボランティアが減ってきた/いったん閉じて、再構築の話し合い
を/再開にあたって確認したこと
*「たまり場ぱれっと」の現場から 菅原睦子
5章 クッキーを製造・販売する作業所を! ――「おかし屋ぱれっと」をつくる
卒業生のほとんどは作業所に/これからの福祉には発想の転換が必要だ/クッキーを製
造・販売する作業所をつくろう!/「おかし屋ぱれっと」のオープン/売上げは順調、
給料もアップ/最初の危機、移転問題/正職員雇用の問題/助成金をもらうか、独自の
運営をつづけるか/通所員と職員の「闘い」も/作業所も経営センスを試される時代に
*「おかし屋ぱれっと」の現場から 相馬宏昭
6章 株式会社で、一緒に働くレストランを! ――「レストランぱれっと」をつくる
「おかし屋ぱれっと」の目を見張る発展/障害者と一般の人が一緒に働く職場をつくり
たい/「レストラン構想」を進めるプロジェクト/スリランカカレーの専門店を/親た
ちの全面的な協力/中心になる人を確保する/バブルがはじけ、お店を移転/障害福祉
が自ら事業を起こし、利益を生み出す時代へ/障害者が一般の人と働けることを、社会
に突きつけたい
*「レストランぱれっと」の現場から 南山達郎
7章 親から自立して、共同生活の「家」を! ――「ぱれっとホーム」をつくる
夢は、さまざまな人たちが共同生活する「家」/グループホームづくりへの挑戦/ハー
ド面の壁を乗り越えて、ソフト面へ/オープンには、クッキーを持って挨拶回り/入居
希望者がいない、利用者が少ない/グループホームと緊急一時保護を同時に運営する難
しさ/ホームを出て、一人暮らしや結婚生活を始めた人も
*「ぱれっとホーム」の現場から 三森紀子
8章 国を超え、障害者の自立援助を! ――「スリランカ Palette 」をつくる
施しによって生かされていた、スリランカの障害者/「一生身につく技術が欲しい」/
「ぱれっと」の親たちへの説得/応募者の切実な「働きたい」という願い/文化や生活
習慣の異なる国での難しさ/スリランカ人スタッフだけの運営へ/障害者の成長と親の
変化が、地域へ波及/また、グループホーム建設資金集めへ
9章 ぶつかりあって、育ち合ってきた
私が誓った二つのこと/親たちとの「闘い」の中から/障害のある人たちが、真に主体
的に生きていけるように/ボランティアを、本物を追求できる若者に育てたかった/ス
タッフを育て、スタッフに委ねる
10章 次代を受け継ぐ者として 南山達郎
二二年を越え、次代へ/「谷口」から「ぱれっと」へ/「なぜ?」という問いかけ/「コ
ミュニケーション不足」という課題/基本は「人が好きか?」/「客観的に見る」とい
うこと/現場に見る「光」/鍵を握るのはスタッフ一人ひとり/新たな挑戦が始まる
| はじめに
「ぱれっと」を創立して二二年間、私は一般市民として、社会の矛盾や理不尽さに対して何ができるのかを自分に問いつづけ、社会にその疑問を発信してきました。そのきっかけは、結婚して子育てに終われているさなか、四歳になる長女の死に直面したことでした。思いもよらない過酷なできごとでした。そのとき、長女の死を通して人の生き方としっかり向きあうことの大切さを学んだのです。
人間である以上、誰もがあたりまえの生活をする権利を持っているにもかかわらず、たまたま障害をもって生まれたことで、その権利を与えられないことの不公平さに、私はどうしても納得できませんでした。そのあたりまえのことから阻害されている現実を私に突きつけたのが、知的障害者との出会いでした。
当時は、一般の市民と知的障害者とのふれあいはほとんどなく、彼らの障害を理解する地域の住民は、ほんの一握りでした。私もその一人だったのです。その後、ボランティア活動を通して彼らとのお付き合いが深まれば深まるほど、彼らの生き方がいかに尊重されていないかを知りました。
そして私は、従来の福祉には「発想の転換が必要だ」ということを痛感したのです。
それは、従来の福祉が、社会で暮らす全ての人々のための、権利としての福祉とはあまりにもかけ離れていたからです。特に知的障害者にとっては保護的福祉の色が強く、市民としての自立性、主体性を重んじたものとは思えませんでした。
地域における「隔離」から「融合」へという「ぱれっと」の挑戦は、まず彼らを社会の前面に押し出すことでした。知的障害者が社会の一員であることを社会に知らしめるために、何もできないと思い込まれている彼らの可能性を引き出す場を、地域につくることから始まりました。
絵を描くときに色を混ぜ合わせ、新しい色を生み出すパレットをイメージして、人を色に置きかえて、いろいろな人との出会いを楽しむ「たまり場ぱれっと」を一九八三年にオープンしました。そして今日まで、知的障害者のニーズに合わせて、地域に一つずつ拠点をつくってきたのです。
知的障害者が自らクッキーを製造し販売する「おかし屋ぱれっと」や、接客業に挑戦する「Restaurant & Bar Palette」は、彼らの可能性に挑戦する働く場となっています。「えびす・ぱれっとホーム」は、親から自立して仲間と共同生活を楽しむ家としてつくられました。そして国際協力プロジェクトとして、スリランカに障害者が働ける場「Palette」をスタートさせたのも、発展途上国の障害者が経済的に自立するための援助だけでなく、「ぱれっと」の障害者がクッキー製造のノウハウを現地の障害者に教える役割を担うことも目的の一つでした。
ところが、新しい福祉をめざす「ぱれっと」の発想の転換が、思いもかけないところで反発を受けることも少なくありませんでした。「福祉」は地味でなければならない、「障害者」は常に保護される立場でなければならないという強い反応に、「ぱれっと」の理念の追求がしばしば揺らぐこともありました。
この本には、ごく普通の一般市民が暗中模索をくり返しながら、知的障害者が地域であたりまえの生活が営める社会をつくってきた取り組みが書かれています。決して武勇伝ではありません。「ぱれっと」の活動を通して、誰もがあたりまえの生活を確立することの難しさを考えさせられた実践記録です。
多くの人たちに支えられながら、スタッフと共に「ぱれっと」を運営してきた、これまでの集大成の記録をお読みいただければ幸いです。
谷口奈保子 |